サイト内の現在位置


2019年12月5日 オフィスコミュニケーションコラム
メールやAIチャットボットの持ちえない、電話の魅力
みなさんはどんな時に電話を使いますか?「お気軽にお問い合わせください! 電話番号は…」
こうしたありふれたキャッチフレーズは、誰もが目にしたり、耳にしたりしたことがあるはずです。従来、問い合わせといえば電話で受け付けるのが一般的でした。
しかし、インターネット上のコミュニケーションが主流となりつつある現在、企業も電話だけでなく、メールやSNSなど、文字で問い合わせを受け付けるケースが増えてきています。
さらには「AIチャットボット」のように、人が直接対応しなくても、お客さまからのお問い合わせに対応できるソリューションも注目を浴びています。近い将来、電話で、人が直接対応するスタイルは淘汰されてしまうのでしょうか。

会社にかかってくる電話は苦手?
新入社員をはじめとする若い世代は、電話でのコミュニケーションが苦手。こんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。とある調査によると20代の約6割の人が「会社にかかってくる電話に出るのが嫌だ」と回答しているそうです。
現在の20代の人たちは学生時代から携帯電話を持ち、メールやチャットで大半のコミュニケーションをとってきた世代です。電話でのコミュニケーションに苦手意識を感じるのも無理はないのかもしれません。
しかし、この調査結果には興味深い続きがあります。 「会社にかかってくる電話に出るのが嫌だ」と感じるのは、若い世代に限ったことではなかったのです。40代でも約6割の人が、50代でも約半数の人が、会社にかかってくる電話に出ることに苦手意識を持っていたのです。
こうした背景には、電話で問い合わせを受けたらその場ですぐに回答しなければならないというプレッシャーを感じてしまったり、高圧的な態度をとるお客さまへの対応に困ったりするといった、人と人とが直接やり取りをするからこそ起こりうる理由があるようです。
従業員に、嫌な思いをしてまで電話の対応をしてもらうくらいならば、”電話を使った問い合わせ対応はやめてしまおう” ”電話は撤去してしまおう” そして、”メールやSNS、AIチャットボットを活用してお客さま対応をしよう”。そう考える企業が出てくるのも当然です。
調査結果出典:ニュースサイトしらべぇ(https://sirabee.com/2017/11/14/20161360530/)

すべての問い合わせを「文字」にすると?
こうした考え方もあって、最近、問い合わせ先としてメールアドレスやSNSのアカウント名を表記し、電話番号を表記しない企業が多く見受けられるようになりました。また、AIチャットボットを活用し、問い合わせ自体を減らそうとする企業も増加傾向にあります。
理由はさまざまでしょうが、こうした企業は電話よりも文字ベースで問い合わせ対応をすることに一定のメリットを見出しているのでしょう。すべての問い合わせをメールやSNS・ AIチャットボットで受け付ければ、電話を受けなくてもよいぶん、「電話が苦手」と思う従業員の働きやすさやは向上するかもしれません。
また、電話対応の時間を短縮することができれば、今まで取り組めなかった新たな仕事にも取り組めるようになります。さらには、問い合わせの履歴を文字で残すことができるので、後々見返したいときにも便利ですし、お客さまとの主張の食い違いを防止できるというメリットもあります。

一方、今まで電話で受けていた問い合わせを文字に置き換えようとする場合、企業は想像以上の努力や工夫をしなければなりません。急ぎのお客さまにはどう対応するか、チャットボットを利用するなら誰がデータベースを管理するのか。そもそも、インターネット環境が整っていないお客さまの対応はどうするのか。
なんの工夫もなしに、単に電話で受けていた問い合わせをメールやSNS・ AIチャットボットに置き換えるだけでは「明らかに利便性が下がった」とお客さまが感じてしまうのは想像に難くありません。
電話の良さはスピード感と熱量にあり
ここで改めて、電話で問い合わせを受け付けるメリットを考えてみます。
1つ目は、電話での対応にはスピード感があるという点。
たとえば、パソコンを購入したお客さまが設定に迷った場合。すぐに方法を知りたいにもかかわらず、メールで翌日以降に回答が来るような仕組みは適切とはいえません。
AIチャットボットも同様。データベースにない質問が投げかけられた際に「わかりません」と回答が返ってきたり、とんちんかんな回答が返ってきたりするようではお客さまは満足するわけがありません。最悪の場合、アフターサービスの悪さが原因でお客さまが離れてしまうケースも考えられます。
電話での問い合わせであれば、タイムリーにお客さまの課題を解決できるぶん、お客さまの満足度を担保できる可能性が高くなります。

2つ目は、「ものごとを伝える熱量」があるという点。
みなさんが何か情報を得ようとしたときのことを思い浮かべてください。インターネットで調べる、本を読む…。方法は多岐にわたりますが、人から直接教えてもらうのが最もわかりやすいはずです。
それは「人」であれば、相手に合わせて説明の仕方を変えることができるから。「この人は不慣れなんだろうな」「今の説明では理解しにくかったかな」。相手の声色や表情を伺いながら、ときには前提となるところまで話を戻したり、ときには言葉を変えて説明したり。これは人だからこそ成しえることなのです。
電話対応も同様。お客さまの声を聞きながら問い合わせに回答することで、お客さまの疑問や課題に臨機応変に対応し、確実に解決することができます。
このように電話での対応には、メールやSNS・AIチャットボットの持ちえない「物事を伝える熱量」が存在するのです。
ツールを使い分けて、次も選ばれる企業へ
情報のやり取りにはメールやSNS、 AIチャットボットも有用ですが、人が行う電話対応にしかできないこともあります。
たとえば、お客さま対応をする中で、お礼を言ったり、謝罪をしたり、交渉ごとを行ったり、といった相手に寄り添った対応は、人が行う電話対応でしか実現することができません。そして、こうした対応には「物事を伝える熱量」の存在が必要なのはいうまでもありません。
メールやSNS、AIチャットボット。お客さま対応をするためのさまざまなツールが存在する中、重要なのはこれらを適切に使い分けられるかです。ツールの選択を誤ればお客さまの利便性を落とす可能性もありますし、最悪の場合、お客さまが離れてしまうことにもなりかねません。
電話に苦手意識を持つ人が一定数見受けられる中、人が人にしかできない電話対応の分野を伸ばすことは、企業にとって使えるツールの選択肢を増やすことにつながります。
適切にツールを使い分けて、次もお客さまに選ばれる企業へ。いま一度、人が行う電話対応の在り方も見直してみてはいかがでしょうか。
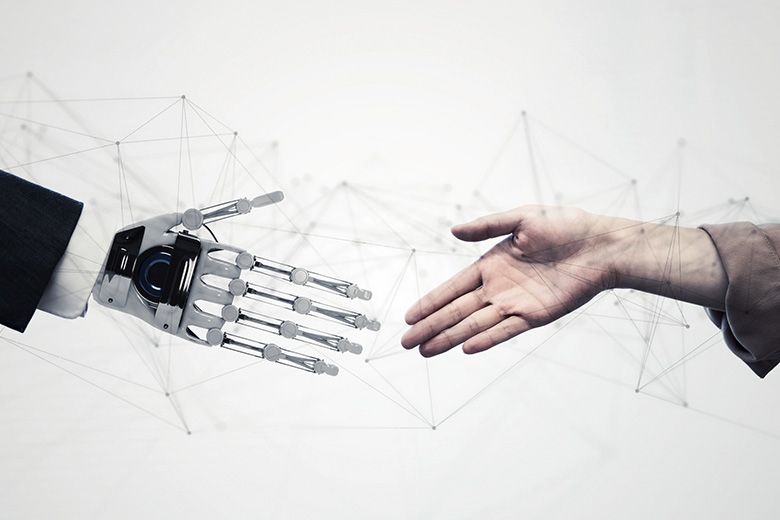
オススメ記事
意外に安価で手軽に構築できる「コールセンター」 必要なのはどんな機能?

5人のオペレーターで6本目の着信に応対するには
非効率な仕事が当たり前になっていませんか

オフィスの日常に潜む非効率な業務
いまさら聞けないビジネスフォンの基礎知識

よく聞くフレーズ「○番に電話です!」 ビジネスフォンはこんな仕組みで動いています
近年注目を集めるコミュニケーションツール、ビジネスチャット

ムダ話が不安? ビジネスでのチャットの使い方
 キーテレフォン/IP-PBX/ユニファイドコミュニケーション
キーテレフォン/IP-PBX/ユニファイドコミュニケーション